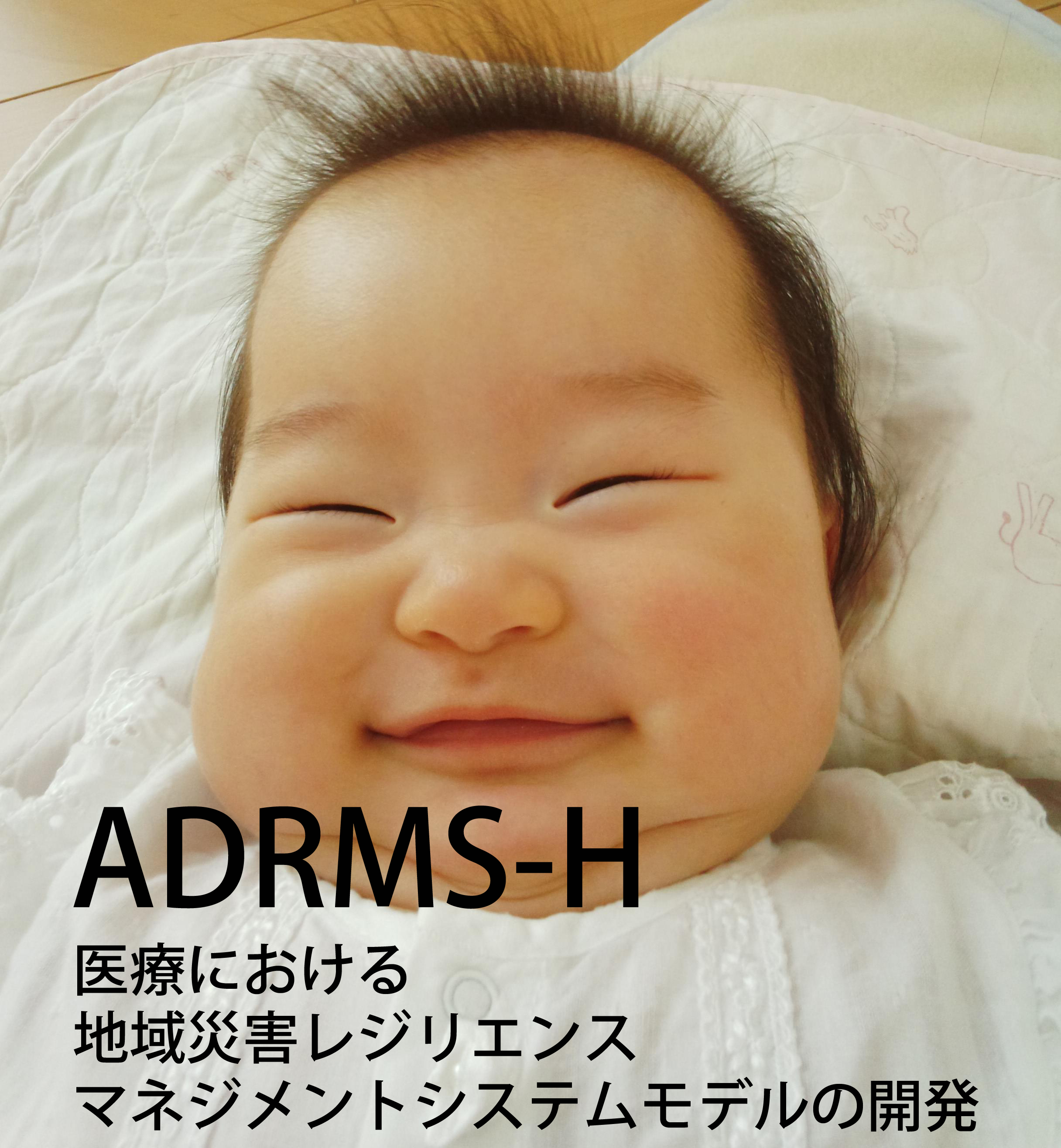新名言集
 サニブラウンの4乗で研究を進めてください.
サニブラウンの4乗で研究を進めてください.- 研究の進捗状況が悪い学生に対し,「急いでください」という意味で先生が放ったセンスのある例え指摘.
1乗から6乗までレベルがあり,サニブラウンの6乗が最もヤバい.しかし,サニブラウンが速いというイメージを持つ人が少なく,
ウケはイマイチであった.来年からはベン・ジョンソンの○○乗でいきましょう!  はまぐりとあさりにしか見えないなあ.
はまぐりとあさりにしか見えないなあ.- またまた出ました,先生お得意の例えツッコミ.これは従来研究との違いが見えない学生の研究に対して放った一言.
たしかにあさりとはまぐり似てますよね〜.この指摘には学生も口を開けてボーゼン.まるで焼きあがってパカっと開いたはまぐりのようでした.  はあ.
はあ.- おもにメールの文面で使われる最恐の二文字.「今日のゼミ休みます」とメールで連絡してきたメールに対し,送りつける二文字.
この二文字が届いた学生は二度とゼミを休まないと心に誓う.「はあ.」が3回届くと恐いことが起こるとか起こらないとか.
「はあ.」が届いたそこの君は要注意だ!
過去の名言集
虫嫌いだし…
投稿論文の執筆は?(^^)
経営システム工学科の平澤茂一前教授がご退任までに10数名のドクター(博士)を輩出なさったことを受けて, 棟近教授もドクターの輩出に力を注ぐと誓われた一言です.
量産体制」という言葉から,次々に優秀なドクターが輩出されていく絵が浮かびます.
ちなみに中間発表の際には,9名中4名ほど言われました.ゼミ発表の際,僕も言われました.
世界新記録並みのスピードで研究をしないと卒業できないぞという 戒めのお言葉を,世間の話題に明るい先生らしく表現されたお言葉です.
もちろん,卒業が取り消されることは無いのですが,教授室から帰ってきた際のK原さんの顔は真っ青でした.
研究を進める上で具体的な計画を立てることが何よりも大切だというありがたいお言葉です。
ちなみにマスター以上でコレをいわれたときは、研究の進捗がかなりピンチなときでしょう、ハイ
目的なく文献を読みあさっても有意義ではないという慈悲深いお言葉です。
学生に申し開きのチャンスを与える最終的なお言葉といってもいいでしょう。
コレをいわれたときは、決して慌てず冷静に受け止め、わかりやすく回答しましょう。
しかしその背後には、
かつてせっかくのデータを無駄にしたマスターがいたぞ、おまえもそうか?
という意味を含めたお言葉です。
中古車の話題が出ないように研究を進めましょう。
そんな時は、先輩や研究室のメンバーと話し合ってみるとトンネルの出口に近づけるよ、
違った観点からの意見も重要だよ、という主旨のお言葉です。
ちなみに、大学院生のあるべき姿とは、月曜から金曜の間10:00~16:00まで研究室の机に向かうことらしいです。
裏を返せば、進むべき時期に進まないようでは研究成果をあげるのは難しいということでしょう。
先生:「10台の体重計の測定能力差を調べるために実験したのか、
測定誤差を調べるために同じ実験を10回やったのか、
どっちがやりたかったの?」
学生:「ア、…はい」
実験を行なうときは、目的・内容を明確にしましょう。
時間をかけて悩み抜いた末に成果が見えてくるという、
先生ご自身の経験に基づく知見あるお言葉です。
ちなみに、この言葉を頂く時も研究に黄信号が灯っているものと解釈すべきです。
間違った方向には進めていないから、そこから考え始めることが研究の本質だ!
という学生を勇気付ける言葉です。
先生から頂く具体的なアドバイスと同じくらい意義深いものです。
提案部分を減らしてでも、それに至るまでのプロセスを明確に示すことが重要だと、優しく諭されたお言葉です。
研究活動そのものを考える上でも重要なお言葉でしょう。
ただし、研究プロセスと研究における苦労話はしっかりと区別しましょう。
おそらくこの時期に明確な返事ができそうなM1であれば、このような質問はされないでしょう。
私は聴かれました。
それを乗り越えていくのが修士だろう4.16.2002
解説のしようもありません。
頑張ろうね、みんな。
そして、我々はそのニーズの意義を評価するところまで考えなくてはならない。
未熟な我々も、先生のこういったお言葉をいただくことで成長してきます。
意味がわからないと直接おっしゃるのではなく、遠まわしに、写実的(?)に表現されました。
このような先生ならではのスパイスのあるエスプリを、学生はいつも心待ちにしております。
まずは、自らが考えられる範囲で精一杯考え抜くことが重要なんだ!
と解釈したのですが、正しいでしょうか…
ただし、最後の最後まで文献調査をしないで、修論発表会で叩かれるマスターが多いから、
それだけはやめてくれ。 そんなこともおっしゃっていました。
必死に分析して出したアウトプットが、固有技術的に見て当たり前過ぎることなんていくらでもあるだろう。
ノーベル賞をもらうような立派な研究でもそんなことはあるよ。
ただ、その当たり前のことを理論と数字から裏付けて語ることが大事なんじゃないかな。
先生も研究を進める上で、いろいろな壁にぶち当たって乗り越えてきたのではないか…
そんなことわれわれ学生に感じさせるお言葉です。
論理的な考え方や洞察力ある分析と同様に、
人前で立派なプレゼンをすることも研究を行う者にとって重要なことなんだ、
学会発表くらいでひるんではだめだ!
私は、君の2年間の修士課程の間に変わってもらいたい。
たとえば、K藤君のように少しは軽はずみな発言もできるようにもなってもらいたいのだよ。
学生を勇気付ける責任感あふれるお言葉です。
表面的にはHP作成者の名前を聞いているだけです。
しかし、暗黙的には「HPというのは結構いいかげんなものが多いから、
安易に文献として引用するのは止めなさい」とおっしゃっています。
学生の皆さん、つまらない文献調査はやめましょう。
金曜日に必修の授業がある4年生を気遣いつつ、現場に足繁く通うことの重要性を説かれています。
ちなみに「マスターは必修の制約がないから、毎日行ってこられるだろ」ともおっしゃっていました。
自身の研究のオリジナリティを出すのに、従来研究の有無は関係ない。
自身のやってきたことの歴史を整理すれば、自ずとオリジナリティは後からついてくるんだ。
他研究どうこうではなく、自らの研究プロセスをしっかり表現することが大事なのでしょう。
「どこでも通用するようなガイドライン」なんて、簡単には確立できない。
それよりも「特殊な状況下において、こんなことを行い、その結果こうなりました」
っていう事実の方が強い説得力を持つし、研究として面白い、ということでしょう。
本文の方に載っている“教科書的な内容”なんかいらない。
拙くても未完成でも自分で試行錯誤したモノの方が、
深く追求する余地もあるしオリジナリティも出てくるのだよ。
教科書的な内容でページ数を稼いで、ゼミの時間を延ばしたり先生の手を煩わせるのはやめましょう。
その次の発表時に再度おっしゃった一言です。
まとめてきたのはいいけど、企業とのやり取りを時系列的に並べただけではいかん。
その中で、自分が果たしてきた役割と、
最終的に得られた研究成果を書かないと、
「卒業論文」にはならんのだよ。
単に企業側のお手伝いをするだけでなく、
主体的な研究者としての立場を自覚しなさい、ということでしょう。
いくら頭を動かしても体がサボっていたのでは、それは机上の空論にしかならない。
体を動かして初めて「研究日記」を書けるんだ。
研究とは座学ではなく自らの五体を駆使して成し遂げるものだという、行動派の先生らしい台詞です。
すばらしい研究なんて一朝一夕でできるものではない。
研究だって、品質管理と同じように継続的に改善していくことにより素晴しいものになるんだ。
君がやってきたことを示さなければ議論のしようがないよ。
ゼミとは、やってきた内容を先生や学生に示すことで、議論を行い軌道修正する場なんだ。
みなさん、頑張ってください。
これは俺の持論だが、卒論・修論で胃潰瘍になるくらいの方がいい。
いい研究とは、多くの時間考えた結果、やっとでてくるものだ。
ストレスがたまるということはそれだけ真剣に考えている結果だからだよ。
また、学生時代に頑張っておけば、会社に入ったときにへっちゃらだよ、ともおっしゃっていました。
意味は、文字通り考えを熟成させなさいということです。
みなさん、熟考しましょうね!
なんでこの人の文献なんだ。
この分野にはこういう研究があって、
だからこの人の文献を選んだんだっていう根拠を示さなければ意味がないだろう。
というありがたい意味を含んでいます。
という仮説に対しておっしゃったお言葉です。
どうしてこの仮説が立つの?君が勝手に思っているだけじゃダメなんだよ。
根拠がないとさぁ。
ということをユニークに表現されたお言葉です。